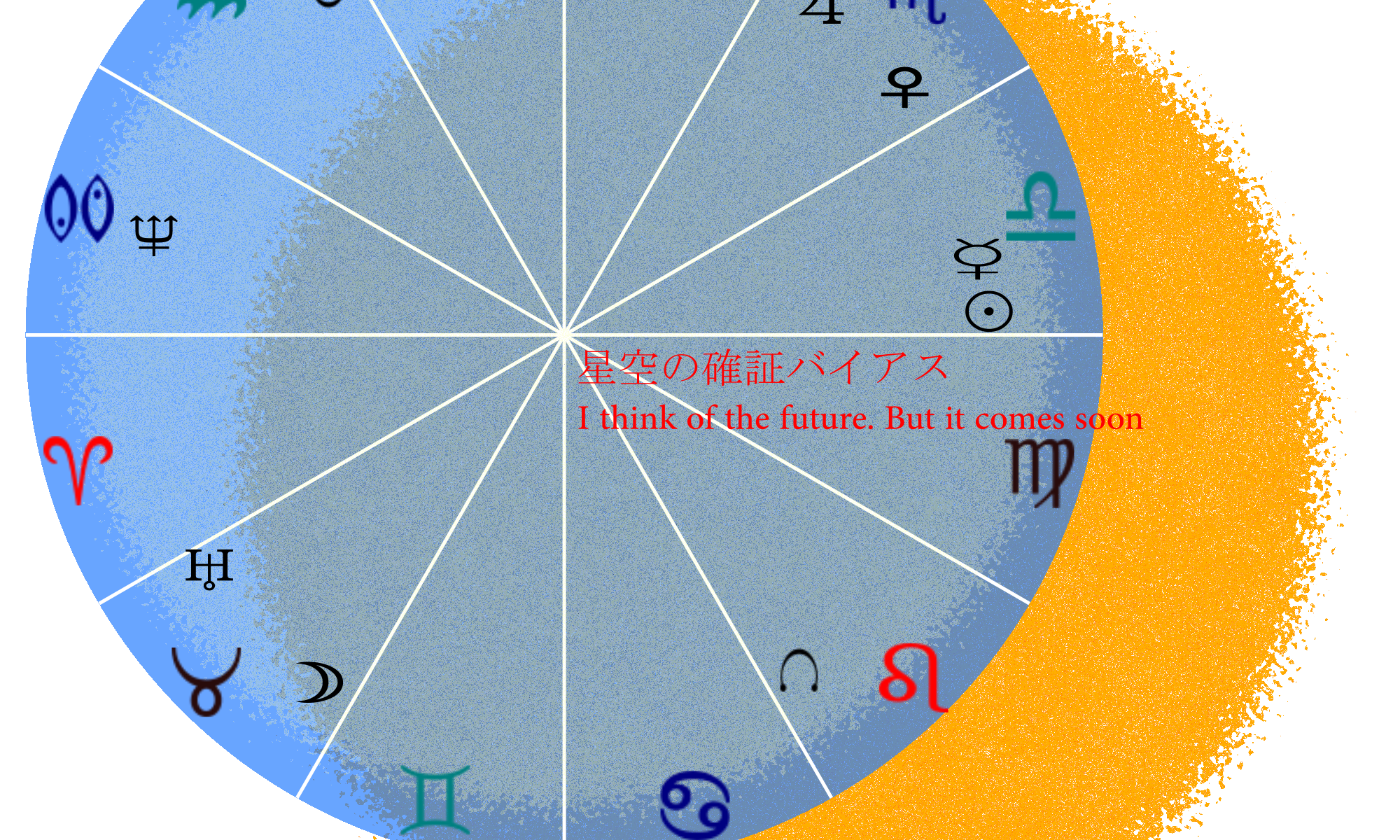序章 花束を抱えて…消えた…
第一章 GOTO 1042
第二章 業務システム説明 完了
第三章 九龍城の奥で何かが壊れた
第四章 マンボウの骨
第五章 救世主に…なってしまった
第六章 二礼二拍手一礼で、そのご高説が成仏しますように
序章 花束を抱えて…消えた…
私はほとほと疲れていたのだ、3か月に一度新規案件を持ち込まれ、もれなくデスマーチである。なぜか「火消し役」というコードネームで呼ばれている状況にほとほと嫌気がさしていた。そんなある日、一人のヘッドハンターから電話がかかってきた。今になって思えば、あの電話に出たことが、間違いの始まりだったのだ。
数か月後
今思うと――あの時は本当に、どうかしていた。
辞表をたたきつけた上司からもらった「データセンターの候補地選定」という名の沖縄旅行から戻ると、『再び』私は辞表をたたきつけていた。
気がつくと、今までは顧客として相手をしていた会社と同一業界の会社の、社内SEという立場の椅子に座っていた。
上司となる部門長に挨拶すると、挨拶が終わるよりも先に彼はこう言った。「ああ、俺、半年後に定年だから。一人になるけど頑張ってね。」
なん…だと…。確かに、この男から現状の引継ぎを受け、
『ゆくゆくは』
部門を引き継いでほしい。そういう話ではあった。
しかし、その『ゆくゆく』というのが半年後であったとは…。
(いや、実はそれすらも誤解だった、定年前3か月辺りから彼は有休をとり始めたので、ゆくゆくというのは、実は3か月後のことだったのだ。)
それから私は、彼を質問攻めにした。
「一体全体どんなシステムを使っているのだ」「会社のネットワーク構成はどうなっているのだ?」「機器の構成は?」「資料は存在するのか?」
資料などという洒落たものは存在せず、彼はそれらの質問には一切答えることはなかった。(回線会社が作ったものであろう電話番号一覧はあったし、「見ればわかる」という一言はあったような気がするので、『一切なかった』というのは少し誇張かもしれない)
最後に彼は、WizDB(ウィズディービー)とかいうドマイナーな開発ツール(開発ライセンスは2005年のものであった。)の開発画面を私に見せ、「これで開発している。」というと、「初めてのWizDB(ウィズディービー)2004」というラベルが張られた一冊のファイルを私に託し、サーバーのパスワードを伝えた。
そして彼は、花束を抱えて…消えた…
第一章 GOTO 1042
WizDB(ウィズディービー)--名前すら聞いたことがない。検索しても、情報がまるで出てこない。
唯一手掛かりになりそうなものと言えば、ネット掲示板のアーカイブに記された「WizDB(ウィズディービー)という開発ツールを使うと、プログラムの知識がなくてもシステムが作れるとのことですが、誰か詳しい方、利用のメリットと利用する際の注意点とかありますか?2002.06.13 22:52:17」という質問だけであった。もちろん、回答などあるはずもない。
私は元上司(と言って良いのかどうかすら怪しいが)が残していったファイルをぱらぱらとめくり、ごみ箱に叩き込んだ。
150枚ほどのコピー用紙が挟まれたフラットファイル。つまり「初めてのWizDB(ウィズディービー)2004」には、『プログラム未経験者でも業務システムが爆速で作れる開発ツール。それがWizDB。』立体的なゴシック体の文字が影まで従えて、レインボーの枠の中ででかでかと踊っている。
目次には
1.WizDBの起動
2.プロジェクトの作成
3-1.データベースサーバーとの接続(MicroSoft Access編)
3-2.データベースサーバーとの接続(Microsoft SQL Server編)
3-3.データベースサーバーとの接続(IBM Db2編)
4.データベースのテーブルの作成 ※MicroSoft Access
5.データの新規作成
6.データの検索
7.データの削除
8.データの更新
10.帳票の作成
11.ランタイムアプリケーションの配布
といったタイトルが並び、事業所マスタをもとに、従業員一覧を作る手順が解説されていた。
角が擦り切れて丸くなったそのファイルにはあちこちに、コーヒーのようなものをこぼした染みが付いていた。
ごみ箱の中のそれには、データの検索ページの先頭に一枚だけ付箋が張り付けられており、エアコンの風に揺れていた。
「今の手掛かりはこれきりだ」私はそう思いなおして、ごみ箱からファイルを拾い上げ、引き出しに放り込んだ。
彼が残した「Administrator」というパスワードをたたくと、サーバーの画面が現れる。画面の左下にWizDBのロゴが見える。
ショートカットをダブルクリックすると、SelectProjectの文字の下に一つだけ、mixlojiと書かれたプロジェクト名があった。
それをダブルクリックすると、
1 フォーム 0 1 2 5 3 true 200 200 400 300 変数1 変数2 変数3
2 テキスト入力 0 0 0 1 1 true 10 20 150 20 定数1 変数2 変数3
3 テキスト入力 0 0 0 1 0 true 10 40 150 20 変数1 変数2 変数3
4 テキスト入力 0 1 0 0 0 false 10 60 150 20 変数1 変数2 変数3
5 ボタン 1 1 1 0 0 true 100 80 60 20 変数1 変数2 変数3
6 フォーム 0 1 2 5 3 true 200 200 400 300 変数1 2 1 変数2 変数3
という羅列が並んでいた。
試しに『1 フォーム 0 1 2 5 3 true…』という行をクリックしてみると、フォームコントロール画面なる画面が現れて、ログイン画面らしきものがそこにあった。
画面の左上でアクティブになっているタブにはフォーム設定と書かれている。
画面の右上には表示設定
縦位置:200 横位置:200 横幅:400 高さ:300という表があった。
それはどうやら、外面設計を行うツールのようだ、プログラム組む人間(つまり私)が見れば、それは、システム作成において、画面のフォーム設計を視覚的に行うことを目的としたものであることは明らかだった。
フォーム設定タブの隣には「ロジック」と書かれたタブがあった。クリックすると現れたのは、
コール サブタスク 48
イベント 集計 63 格納 i01
処理の流れらしきものが並んでいる。だが、その意図は読めない。
『プログラム未経験者でも業務システムが爆速で作れる開発ツール。それがWizDB。』の正体は、おぞましい化け物のようだった。
プロジェクトの中に並ぶ2000行ほど羅列――その一行一行に、フォーム設定とロジックが、ぬるりと這い回っていた。
その奥では、サブタスクという名の小虫が羽音を立てている。
私は軽い眩暈を覚えながら、画面をスクロールしていく。
その先に私は嫌なものを見つけた。
82 データコントロール 0 0 0 0 0 true 100 80 300 150 変数1 変数2 変数3
82 ボタン 0 0 0 0 0 true 100 100 60 20 変数1 変数2 変数3
83 分岐 0 0 0 0 0 true 200 200 400 300 変数181 1 定数2 9999変数3 = false GOTO 1024
GOTO 1024……
第二章 業務システム説明 完了
GOTO 1024……思わずWizDBの画面を閉じた。次はWizDBのショートカットの隣にあるSQLServerManagementStudioのショートカットをダブルクリックする。
今の私にとって、システムのデータベースがMicrosoft SQL Serverであることだけが、唯一の心のよりどころだった。
管理者権限のパスワードに「Administrator」と入力するとあっさりと画面が開き、
mixlogiと書かれたデータベースをクリックすると、データの一覧がそこに現れた。
そこには「商品マスタ」とか「日次データ」と書かれたテーブルのリストが200ほど並んでいる。
「日本語かよ」そういえば、『初めてのWizDB(ウィズディービー)2004』の中でもテーブルの作成例は日本語だったことを思い出しながら、中身をいくつか見ていく。
私はすでに、日本語でデータ定義されていること自体に苛立つ気力すら失っていた。
「商品MST」と「商品マスタ」「商品マスタ」は、用途が違うのか?開けてみると、全く同じに見える。
もう一度、よくよく目を凝らしてみると、微妙に何かが違う。それは『区』であったり、『区分1』であったり、『あるなし』というフィールドの存在の、ほんのわずかな違いでしかないのだが、少しずつ違う形をしていた。
「もしかすると、これらは、3つで一つの情報が形作られるのかもしれない。」
だとすれば、これらをひとつなぎの情報にすることができるかもしれない。私はささやかな期待をもって、
select [商品MST].[商品コド] as A, [商品マスタ].[商品コード] as B from [商品マスタ]
left outer join [商品マスタ] on([商品MST].[商品コド]=[商品マスタ].[商品コード]);
という使い慣れた呪文をキーボードに打ち込んだ。
エラーになる、目を凝らしてよく見ると呪文が少し間違っている。たったこれだけの長さであるにもかかわらず、気が付くのに5分もかかった。
select [商品MST].[商品コド] as A, [商品マスタ].[商品コード] as B from [商品MST]
left outer join [商品マスタ] on([商品MST].[商品コド]=[商品マスタ].[商品コード]);
すると、右側の列にNULLの文字が並び、時々31936とか、45637といった文字が現れる。
今度はleftをrightに変えてみると同じく、左側の列にNULLが並び、時々31936とか、45637といった文字が現れた。31936は7回も連続している。
うん、知ってた。私の中で何かが、途切れた。
『受領印チェック』テーブルの中にある『受領印テック』ってなんだよ、先端企業か?受領印の世界に革命でも起こすのか?
『商品MST』に『商品マスタ』どっちを使ってるんだ、両方か?両方なのか?ついでに『商品マスタ』も使っていやがるのか?
納品日が数字なのはなんでだ?2022年4月38日が存在する世界線なのか?
おまけに、受注日ときたら、なんで『2022年4月1日』と『2022/04/01 』『令和3年04月02日』が仲良く並んでるんだよ。
『44652』って、日付か?Excelか?Excelなのか…?1900年1月1日から何日たったか数えろってか?
『new発注データ』と『発注データ2』ってどっちが新しんだよっ!大体『発注データ』はどこに消えやがった?
なんで電話番号の後ろに全部スペースつけて長さそろえてんだよ。いやがらせか?いやがらせなんだな。
全部のテーブルにprimary keyがないじゃないか。
バカか?アホか?愚か者か?それとも全部か?
『日次データイオン』の中に何でダイエーとイズミヤのデータが入ってるだよっ。挙句の果てには『日次データ』『阪急日次データ』に『new_matsuzakaya日次データ』だと?
だったらなんで、【伊勢丹】がないんだっ!
一通り吐き出してから私は、テーブルとフィールド名を出力し、タバコを吸いに席を立った。
戻ってくると、プリンターには80枚ほどの印刷物がたまっていた。
私はそれを手に取り、引き出しを開けてハサミを取り出す。
一つひとつ、テーブル名とカラム名の塊を切り分けていく。
床にはコピー用紙の切れ端がぱらぱらと落ちていった。
静かな作業だ。だがその手は、怒りと諦めの熱をまだ帯びていた。
私は知りたかった。
このシステムが、どうして、こうなってしまったのか。
どんな意図で作られ、どんな流れでこうなったのか。
かつて上司だった男が「システムの説明をする。」そう言った日のことはよく覚えている。
覚えているも何も、わずか30分いや20分ほどのことだ、忘れる方が難しい。
「少し時間ある?」昼飯のカップ麺をすすっている私の肩をたたくと、「今うちで使っているシステムの説明をするから。」そう言った。
男は私と私に与えられたWINDOWS7のデスクトップ機の間に体を割り込ませると、デスクトップ上にWizDBのロゴのショートカットを作った。
ショートカットの下には『業務システム.exeショートカット』と書かれていた。
ダブルクリックすると、ログイン画面が開いた。
社員番号、と書かれた入力ボックスと、『確定』ボタンがひとつ。
背景には、やけに鮮明で解像度の高いトラックの画像。
入力ボックスに『1』と入力して確定ボタンを押す。
「別に入れなくても動くんだけどね」そういいながら、男は確定ボタンを押した。
画面の左端に20220301と今日の日付のようなものが既に入力されていた。
今日の売上と書かれたタイトルの下には事業所の名前が並んでいる。
その横にはおそらく今日の売上金額であろう数字が並んでおいた。
「事業所、本社の次に神戸がきて、その次が岩手、名古屋、広島、愛知になっている順序にルールはあるんですか?」
「うちはこの順番で見るのが習慣。」
「並んでいる事業所名、聞いている事業所と数が合わないんですが。」
「ああ、作ってない。それで、この箱に日付を入れて確定ボタンを押すと、売上日が変わる。」
「それで、このボタンを押すと仕事で使う画面になる」
今度は画面の左下に並んだ『確定』『マスタ』『その他』と書かれたボタンのうち『確定』をクリックする。そこは、『売上入力』とか、『請求』あるいは『請求処理』『日次処理』や『配車』『ゼロ処理』という文字が書かれたボタンが並んでいた。
「これが、業務メニューで売上とか請求、支払いは全部ここから。」
「わかった?」
「これは運送会社の、誰の荷物をどこに届けるかを管理するシステム。ですよね?」私はボタンから読み取れるいくつかの理解できる言葉と、この会社の業務から考えれば誰にでもわかる、至極簡単なことを言った。
「そう。正解。わかったみたいだね。」
全然わかってなどいない。私は質問を続けた。男は私の質問を手でさえぎる。
男の顔には、面倒くさいという言葉が書いてあるかのようであった。
「そういえば、昼から出る用事があったんだった。」
男は何かを思い出したような顔を作り「忘れてた、忘れてた」とつぶやきながら、立ち去った。
カップ麺は、まだ食える程度にのびていた。
その日、彼の業務日報には、こう記されていた。
――『業務システム説明 完了』
第三章 九龍城の奥で何かが壊れた
業務システム説明が完了したらしき日から、数日後--深夜。
MixLogiと向き合うには、静けさが必要だった。
人の声も、業務の気配もない時間。
それは、私の集中力とか、そういう問題ではない。もっと物理的な理由だ。
深夜、おそらくすべての従業員が帰宅しているであろう時間を狙って、システムの情報が格納されるデータベースのバックアップを取る。
触っている途中で、何が起こるかわからない。
画面には、野放図に操作ボタンがあふれている。あちこちに処理という文字が見える。
中でもとりわけ多いのが専用という文字だった。それは顧客名らしきものの後ろについていたり、あるいは人名のようなものであったりした。
ほとんどが名詞のみが書かれているボタンの群れは、一体全体どう動くのか。飛ぶのか、跳ねるのか、あるいは潜るのか。
皆目見当がつかなかった。
そんなものを、他の誰かが触っている時間に触れるわけがない。いつでも今に戻れる。そういう状況でなければ、怖くて触れやしない。
そんな行為は、パラシュート無しでスカイダイビングをするのと同じだ。つまり、自殺だ。
テスト環境?そんなものは用意されてなどいない。今動いている目の前の現物。これ以外には、何もなかった。
メニュー画面に並ぶボタンをひとつづつ押し、スクリーンショットをとってはエクセルシートに張り付けていく。そこから、画面の流れを、処理の動きを、システムの息遣いを見つけ出そうと試みようとして、
――やめた。
メニュー画面は原色の背景で、さまざまな大きさのボタンが敷き詰められている。一貫性のない色と文字の洪水が、私の目を焼く。
意を決して、いくつかのボタンを押してみる。そのほとんどは、入力ボックスが二つ三つあるだけの、やけに簡素な画面だった。
本当にそれ以外には何もなく、何かが動くのかどうかもあやしかった。
そして時折、唐突にボタンだらけの別の画面が開くのだ。
唐突に開いた画面はもっとたちが悪かった、ただ顧客名らしき名前と、人名らしき名前が、大小さまざまなサイズで並んでいるのだ。
ある画面には、松坂屋と書かれたボタンが4個も並んでいた。
あちこちに、『危険使うな』とか、『触る前に全社に連絡する』とか、『イオンでは使わない』といった注意書きが呪符のように張り付けられている。
これは、構造物ではない。
無計画に増築され、不安定な場所に無理やり据え付けられている。隙間があればそこは何かに利用され、思いつくがままにのびていくのだ。
ある部屋には、トイレが洋式と和式で2つあり、なぜか和式トイレには専用の冷蔵庫が備え付けてある。
飲み水の配管と汚水の配管が絡み合い、ポタリポタリと水滴を落としている。
入り口には使えるが出口には使えないドアが三つもあって、出口は天井のダクトにつながっている。
そう、それはまるで――九龍城のようだった。
眩暈と、頭痛をこらえながら、せめて、という思いで、
「運賃テーブル」という名の扉を開けた。このボタンには昼間あたりをつけておいたのだ、
「運賃テーブル」と「運賃テーブル2」だけは、対応するデータの予想が付いているのだ。
これがどう動くのか、それだけでも知りたかった。
ボタンを押してみると、素っ気ない画面。顧客コード、顧客名、区分、単価……それだけ。
「運賃テーブル2」はどうか?
開いてみる。──同じだ。
だが、下にスクロールしようとして──止まった。
スクロールバーが、どこかで“引っかかって”動かない。
試しにキーボードで動かすと、今度は快適に滑る。
そして見つけた、空白の行。
入力してみた。「987654」
……入ってしまった。
嫌な予感がした。
データベースを開き、確認する。──ヒットしない。
入力して、再確認。──ヒットしない。
場所を変えて、また入力して、再確認。
……ついに、単価に打ち込んだとき、反応した。
987654──ヒット。
次に単価を「987652」と打ち換えてカーソルを動かした。
画面が止まる。
数秒後、MixLogiは落ちた。
九龍城の奥で何かが壊れた音がした。
第四章 マンボウの骨
怒りと諦めの熱をまだ帯びた手の中には、テーブル名とカラム名の塊が書かれた紙束があった。
私は会議机の上に模造紙を広げた。
紙束を一枚づつめくり、
『日次データ』と思わしきテーブル名を見つけたるたび、模造紙の中央に配置していく。
『日次データイオン』『阪急日次データ』に『new_matsuzakaya日次データ』…『日次データ(旧)』…
最後まで紙束をめくり終えると、中央に並んだカラム名を観察する。
少しだけ中身の毛色が違うように見えるものは少し離して、同じように見えるものは逆に少し重ねる。
『日次データ』の次は『発注データ』を探して、『日次データ』の上に塊を作っていく。
上司だった男の性格を予想し、同じことを別の言葉で言っているもの、同じ言葉なのに別の意味を持つもの。それらを探しながら、模造紙の上に言葉の地図を作っていく。
ゆっくりと男の過去に、歴史に、潜っていく。
『商品MST』に『商品マスタ』『受領印チェック』…
一つ一つ、観察し、並べ替え、ずらし、上から下に、右から左に、流れのようなものを探す。作り上げていく。
引っ掛かりを感じるものがあれば、マーカーを引く。
慎重に、よほどの引っ掛かりがない限りマーカーは引いてはいけない。
全部に引いてしまっては、地図はモザイクタイルに成り下がる。
大切にしているもの、宝を探し出すのだ。
システムの画面を追おうとした。利用者の行動を追いかけようとした。プログラムのソースを追いかけようとした。
しかしそこには、何の秩序も、目的も見出すことはできなかった。
私は知りたかったのだ。
MixLogiが、どんな物を食べて、何を嗅いで、何を見ている。どんな生物なのかを。
MixLogiが、どんな風を受けて、何に流され、何処へ向かう。どんな帆船なのかを。
MixLogiが、どんな場所に建つ、何に耐えて、何を守護する。どんな要塞なのかを。
MixLogiが、どんな意図を持ち、何を支えて、何を示すのか。どんなシステムなのかを。
私は並べていく。まるで恐竜の化石を復元するように、慎重に紙片を並べていく。
私は並べていく。どこにこの骨が置かれ、何処とつながっているのか、前後のつながりのように見えるものだけを頼りに、慎重に紙片を並べていく。
私は並べていく。その肋骨を、その距骨を、その仙椎を、その指骨を、崩さないように、慎重に紙片を並べていく。
私は並べていく。どのデータが、どの情報に依存し、どのようにつながっていくのか、名前だけを頼りに、慎重に紙片を並べていく。
全ての紙片を並べ終えると私は、それを崩れないように、そっとテープで止めて固定していく。紙片の間に線を引き、書いては消して、時にそっとはがし、並べ替え、線を引いていく。
それはまるで、骨格標本に添え木を当てる作業のようだった。
これは、データの構造という骨組みから、もともとの、全体の姿を想像する。
MixLogiというシステムの骨格標本を作る作業だった。
一通り並べ終えて、私は少し後ろに下がる。全体の形が私の目に飛び込んでくる。
それはまるで、空を飛ぶ鳥のようであった。いびつな頭に大きな羽をもつ、鳥の姿のようであった。
しかし今にして思えば、私はそこに、鳥であってほしいという夢を見たのに過ぎない。
MixLogiというシステムが、目的をもって、どこかに渡っていく、渡り鳥のように、何かを目指したシステムだと信じて、夢を見て、幻を見たのだ。
今にして思えば、あれは、マンボウの骨だった。
流れに押されて流され、ゆらゆらと泳ぐ。マンボウの骨だったのだ。
しかし、マンボウなりに必死に泳ぎ、その場所にとどまるために必死に、ゆらゆらと踏みとどまっているのだ。
あれは、確かにマンボウの骨だった。
第五章 救世主に…なってしまった
何もわからなかった。男からの、業務システム説明はもちろん、実物の画面を見ても、本当に何もわからなかった。
これは、実際にMixLogiが使われているその姿を見るしかない。
男に連れられて、通り一辺倒の挨拶回りで利用者たちの顔は見た。それでは全く足りない。
挨拶回りに行った日のことは覚えている
「M君。今度システム担当として俺の後任になるから、困ったことがあったらどんどん相談して。」
「Mと申します。よろしくお願いします。」
神戸事業所のメンバーは立ち上がり、拍手で私を迎えてくれた。
「それで、この事業所ではどんなお仕事をされているんですか?」
「イオンさんと、阪急さん、あとは細かいお客さんがいっぱい。」
「なるほど、一番大きいのは?」
「阪急さんかなあ。」
「阪急さんではどんな…。」
私が立て続けに質問を繰りだすと、男は私を手でさえぎった。
「忙しいから、あんまり引き止めちゃダメ。一人ずつ紹介するから。」
そういうと私を立ち上がるように促した「ごめんね、邪魔して。」といって、私を手招きし、
「Uさん。ここの事務所で一番長い女性。こう見えて5人子供がいる。」
「Hさん。筋トレが趣味。」
そう言って、一人ずつ案内して回る。三十分ほどで全員への挨拶を済ませると、コーヒー驕ってやる。と男は言って、自販機に小銭を入れた。
「で、大体わかった?」
なにが?
「じゃあ行こうか、この近くだとおいしいステーキ屋がある。驕る。」
そう言って、近所のステーキチェーンに連れられた。
「御馳走さまです。」
「領収書の宛名は…これで。」そう言って男はレジで名刺を出している。
「じゃあ、帰ろうか。」「もう少し、実際に作業している現場と確認しておきたいので、良いですか?」
男の顔には、面倒くさいという言葉が書いてあるかのようであった。
倉庫でフォークリフトに乗っている男に声をかけ、手に持っている紙を見せてもらう。
実際に扱われる商品を眺めて、どう置かれているのかを確認する。荷物が到着すれば、何を会話しているのか聞き耳を立てた。
小一時間ほどそうしてから事務所に戻ると、男はノートパソコンを開き、デジタルカメラのカタログを見ていた。
「遅かったね。現場歩き回るのが趣味?」いかにも不満気だ。
「そうですね、二足歩行が趣味です。カメラ、お好きなんですか?」
「そう、退職したらもっと本格的にやろうと思って……。」
CanonとNikonの違いについて、2時間も聞かされた。
これは、実際にMixLogiが使われているその姿を見るしかない。
男に連れられて、通り一辺倒の挨拶回りで利用者たちの顔は見た。それでは全く足りない。
「明日、一人で現場を見に行ってもいいですか?」男の手帳に研修・懇親会という文字が見えたその日を狙った。
「いいけど、邪魔するなよ。」
そうして、私は再び神戸事業所にいた。
朝礼と呼ばれる儀式で従業員に交じって社訓を唱和していた。
「今日も一日よろしくお願いします。」というと、散り散りになっていく従業員を呼び止める。
「すいません。今日はちょっと現場で実際にMixLogiが使われているところを見てみたくて来ました。色々教えてください。」
そう言って私は、深々と頭を下げた。
筋トレが趣味だというHさんがMixLogiの画面を立ち上げる。私は素早く彼の背後に立った。
筋トレ男はメールを立ち上げ、何やらエクセル操作をしている。
「それは、何をしているんですか?」私が訪ねると「津田沼商店さんの登録作業」という言葉が返ってきて、筋トレ男はかかってきた電話に出た。
「あー、お世話になります……今日の納品分ですか?……」そう言いながら、目の端でパソコンの画面を追い、マウスを動かしている。
体が覚えているのだろう、少しずれた場所でマウスを右クリックして「おっとっ。」とつぶやいた。
筋トレ男の手元に開かれたノートに目をやると、随分使い古されたそれには。
柳瀬産業処理と書かれていた。
P列を切取→A列を選んで貼付。Q列を切り取り→E列に張り付け。J列からT列まで選ぶ→削除と書かれている。
名前を付けて保存→csv選ぶ→デスクトップ→CSV→イオン受注に上書き。
イオン専用→3→F3→F4→終了
と書かれている…。
眺めていると筋トレ男はその津田沼商店様かららしいエクセルファイルをイオン受注に上書きして、
区分と書かれた入力ボックスに5と入力して→F3→F4→終了した。
「ええっと、今やられていた作業は、津田沼商店様からイオン様へお届けする商品の登録。ということでしょうか?」
私は観察の結果予想される業務内容を尋ねた。
「ええっと多分、そうなのかな。共有メールに津田沼商店さん宛のメールが届いたらこの作業をする。」
筋トレ男はそう答える。私はそれ以上は諦めた。
「同じ画面で他のお客様でもするんですか?」
「他の仕入れ先もする。」
「その区分は、他の仕入れ先でも同じですか?」
「全部違うし、エクセル作業もそれぞれ違う。全部覚えるの大変だったけど、今は見なくてもできる。体が覚えた。」
筋トレ男はそう言って胸をはった。大胸筋がピクンと動いた。
「こっちも使うけど、見ます?」
ショートボブの女性が声をかけてきた。5人も子供がいるというUさんだった。
ショートボブのデスクトップには、『阪急用処理』と書かれたフォルダが浮かんでいた。
フォルダの中は『Chou-Chou(11)→F3→F4→終了』や『DearDrop(35) →F3→F2→終了』と書かれた無数のショートカットで埋め尽くされていた。
その中に見覚えのある名前があった。『柳瀬産業(7)→F3→F4→終了』という名前のフォルダだ。
「柳瀬産業さんって、阪急とも取引あるんですね。」
「今はないけどね。ありがとう消さなきゃ。」
ショートボブはそう言うと、躊躇なくそれをごみ箱へ移動させた。
「あ、ちょっと、Hさんのノートには柳瀬産業さんの場合3って書かれていたと思うんですけど…」
というと、筋トレ男が「今は7。」と声を上げた。
「イオンさんの場合は、エクセル作業全部一緒だけど、阪急さんの場合は取引先によって違うの。ちょうどDearDropからメールが来たからやるね。」
「このエクセルを開いて。」
そう言いながら、メールに添付されたCSVファイルを開いた。
DearDrop(35)→F3→F2→終了のショートカットを開き、中にあるエクセルを開く。貼付と書かれたシートにCSVファイルの内容を張り付けた。
取込というシートを開く。保存先にデスクトップ→csv選ぶ→デスクトップ→CSV→阪急受注を上書き。
私はショートボブの作業の手を止め、保存先を観察した。そこは、デスクトップではなくサーバーの阪急と書かれたフォルダの中だった。
「やることが多くて大変ですね。新しい取引先が増えたときとかどうされているんですか?」
私は膝から崩れ落ちそうになるのを必死でこらえながら、声を絞り出した。
「システムに言って作ってもらう。」
ショートボブはそう、さらりと言った。
慣れた手つきでMixLogiの阪急と書かれたボタンを押し、35→F3→F2→Escと押した。
「簡単でしょ。」とほほ笑む。
「このショートカット私が思いついて、業務改善案だしたら業務最適化委員会から表彰されたの。クオカード500円もらった。」
ショートボブはそう言って、鼻を上に向けた。どうやら、それを自慢したかったらしい。
それから数日後の事だ。早朝通勤途、私は少し急ぎ足で歩いていた。携帯電話が震える。
「助けてください。ショートカットがない。」
電話をとるといきなり、ショートボブは早口で、言葉のショットガンを私に食らわせた。
「出社したらデスクトップにあるはずのショートカットがない。」
「DearDropからメールがきている。」
「処理できないと荷物が止まる。」
「私は何もしてない。」
と言って喚いている。当時まだ上司だった男は、電源を切っている様子で、つながらないらしい。
「落ち着いてください。まずは大きく息を吸って、吐いてー。吸って―、吐いて―。じゃあ一回手をたたきましょうか、よーお。」
パンッという音がした。素直に手をたたいてくれたようだ。
「落ち着きました?デスクトップから気が付いたらショートカットが消えた。ということですね?」
「そう、私は何もしてない。」
「OKです。よくあることです。今パソコンの前にいますか?」
「います。」
「じゃあ、何でもいいのでフォルダを開くことはできますか?」
「フォルダ?」
「ええっと、じゃあ、画面の下の方に、黄色いというか茶色い四角のアイコンは見つけられますか?」
「ない。」
「なんか、こう、ファイルケースみたいな。」
「あった、これかな。」
「クリックできます?」
「開いた。」
「じゃあ、左の方に、デスクトップとか、PCとかあるのはわかりますか?」
私は歩きながらパソコンの画面を頭の中に描き、思い出していた。
「ある。」
「PCを押してください。そうすると、ローカルディスク(C)って出てくると思うので、それを押してください。」
「押した。」
「じゃあ、右上に検索ってあると思うんですけど。」
「あった。」
「そこに、終了と入れて、エンターターキーを2回押してください」
全角や半角であいまいにならず、できるだけ検索結果が少なくなりそうな言葉を選んだ。
「押した。」
「じゃあ、二礼二拍手一礼で、ショートカットが出てきますようにってお祈りしましょうか」
電話の向こうで、小さな笑い声が聞こえた。ちゃんと柏手の音が聞こえて、遠くから笑い声がした。
「いやーでも大変ですね。朝早くから。いつもこの時間には仕事をしてるんですか?私、朝が弱くて、今も遅刻しないように必死でしたよ。でも、お電話いただけたおかげで、遅刻してもサポートですって。堂々としていられます。ありがとうございます。」
できるだけどうでもいい、どうでもいい話をして時間を稼いだ。待ちが長くて途中で閉じられたらたまらない。
「あー出てきたー。助かったー。ありが」
「出てきたやつの下に、デスクトップとか書いてあると思うんですけど。」
「書いてある。」
「デスクトップって書いてある後ろ読んでもらえますか?」
「事業所報告って書いてある」
「デスクトップに、事業所報告ってありますか?」
「あります。」
「そこ開けます?」
「あったー。」
「マウスでつるっと、移動させちゃってたみたいですね。では、今度コーヒー出してくださいね。ブラックで。」
「ホット?アイス?」
その日から私は、事業所で、救世主と呼ばれることになった。お供え物と称して、毎度毎度ホットでブラックコーヒーが出てくる。
救世主に…なってしまった。
第六章 二礼二拍手一礼で、そのご高説が成仏しますように
「利他の心が大事なんだよ。」コーチングセミナーから帰ってきた翌日、男は私に向けてやけに熱く語っている。
さて、思い出して書こうとしているのだが、何を言っていたのかが全く思い出せない。まったくだ。
私は今、必死に、この物語を語り始めてから初めて必死に、思い出している。
なぜならこれから男が話す言葉たちは私の中の利他行動とは違うものだったからだ。
語録の引き出しに入れるのもおぞましい、言葉の数々だったからだ。
それは私の中で大切にしている言葉の数々を、無残に引き裂き、歪め、叩き潰すようなものだったからだ。
犬に喰わせとけ。いや、犬が腹壊すから駄目だ。と思った感想の記憶しかない。
「俺はさ、嬉しかったんだよ。昨日お前が自分から現場に行かせてくださいって言ったの。
やっぱりシステムっていうのは、現場に寄り添って、現場の声をちゃんと聴いて、現場が求めているものを作ってやるものだと思うんだよ。」こんな風に始まった。と思う。
退職するあなたが、なぜ今更、コーチングの研修に?という疑問が頭の中で渦巻いていた。
「俺はさ、現場が欲しいっていたものを作ってやるのが一番だと思っている。それで、どう?何か悩みとかある?」
おそらく傾聴の姿勢というあたりに『学びがあった』のだろう。男は前のめりになって、左耳をこちらに向ける。耳に手でも当てそうだ。
きっと、相手をほめるとか、自己開示だとかいう『学びも』あったに違いない。
「悩みですか、MixLogiがいろいろやりすぎてて、相当色々…現場の声を聴いた結果なんでしょうね。こりゃあ、大変だぞって。」
私が言い終わる前に男が私の言葉を遮った。傾聴の姿勢は学んでいなかったようだ。
「そうだろう。これは、俺が15年かけて現場の声に答え続けてきたものだからな。」
男は自分のパソコンのデスクトップに浮かぶWizDBの開発画面を振り返る。
「でも心配はいらない。お前はできる。何しろWizDBはプログラム知識なんてなくても開発ができる。俺もゼロから勉強してこれを作った。」
そう言って男は「初めてのWizDB(ウィズディービー)2004」というラベルが張られた一冊のファイルを私に渡した。
「俺もこれで勉強した。最初は色々聞いたが、1年ぐらいで大体わかった。Javaのプログラム経験があるお前なら、見るだけでわかるはずだ。」
「最初は色々聞いたって、どこに聞かれたんですか?」
「俺がもともといた会社。俺はそこで営業していたんだよ。これを、売ってた。」
「そうなんですか、それで、その会社は今でもサポートを……」
「潰れた。逃げておいて正解だったよ。」
「それで、神戸事業所はどうだった?」
「何と言うか、皆さん凄いなあと、あの複雑な操作をもう体が覚えているというか。」
皮肉のつもりだったが、男は嬉しそうだ。
「そうだろう、あそこの事業所は勉強熱心で、Uさんのデスクトップの工夫、見た?あれ、俺が業務最適化委員会立ち上げた時に、最初に最優秀賞あげたんだよ。工夫がすごい。
今でもうちの会社、業務最適化委員会続いてて、これはもう文化だよね。全従業員が月に一個、何か工夫して、会社に上げるの。会社がどんどん良くなる仕組み。
仕組みづくりって大事だよね。放っておいてもどんどん良くなるこういう仕組みづくりをするのがシステムの仕事だよね。
ああ、お前もそのうち月に一個ノルマになるから、いまはまあ、会社の事よくわからないと思うから見逃してるけど、これは義務。」
「H君もね、すごいんだよ、こんなのがあったらいいのになって言うのをどんどん言ってくる。そういうこと言われたら、作ってあげたくなっちゃうよね。」
「うちのやってることってさ、利用する現場の声を吸い上げながら一緒にシステムを作り上げていっているんだ。最先端の、アジャイル開発ってやつだ。」
「結局さ、そういうのにこたえていくのが人間力を磨くってことなんだよ。目の前の人間に真摯に向き合って、対話しなきゃいかん。それが人間力なんだ。勉強だよ勉強。」
私が口をはさむ余地なく、男は話続けている。その目はどこか遠くを見ていて、男の目には、私のことは映っていないようだ。
「だから、俺もそうあろうと思う。人の上に立とうとするものは、誰よりも低い場所に身を置かなきゃならん。何事も実践だよ実践。短い間だけど困ったことがあったら何でも言ってくれ。力になってやる。」
ああ、この男は素直なのだ、セミナーで聞きかじった、薄っぺらい『気付き』を今一生懸命実践しようとしているのだ。
言葉の端々に、作って『やる』、力になって『やる』、の一言一言に、上から目線と、高い場所に身を置こうとしていることには気づいていないようだが、彼なりに理解できた『気付き』を実践しようとしているのだ。
MixLogiもまた、この男なりに一生懸命に、誰かの役に立とうと、必死で手探りで、暗がりの中を一人で、作り上げたのだ。
素直に現場の声を聴き、言葉通りに受け止め、一生懸命に作りあげたのだ。
だからこの男にとって、MixLogiは愛おしく、大切なものなのだ。
だから、あえて言おう、少し考えれば予見できることを考えず、ただ目の前にあるものだけに右往左往してはだめだ。
「いちどに道路ぜんぶのことを考えてはいかん。わかるかな? つぎの一歩のことだけ、つぎのひと呼吸のことだけ、つぎのひとはきのことだけを考えるんだ。いつもただつぎのことだけをな。」またひとやすみして、かんがえこみ、それから、「するとたのしくなってくる。これがだいじなんだな、たのしければ、仕事がうまくはかどる。こういうふうにやらにゃあだめなんだ。」そしてまたまた長い休みをとってから、「ひょっと気がついたときには、一歩一歩すすんできた道路がぜんぶ終わっとる。どうやってやりとげたかは、じぶんでもわからん。」彼はひとりうなずいて、こうむすびます。「これがだいじなんだ。」
モモ ミュヒャエル・エンデ作 大島かおり訳
岩波書店1976年9月24日発行
1989年12月20日第41版
48ページ、49ページからの引用
いつだってつぎのひとはきのことを考える。しかし、まずは最初に、道路全部のことを考えて絶望し、祈るという工程が必要なのだ。
それが終わってから、一息ついて、あとは目の前のことにひたむきになるだけだ。
私は、この男のその一生懸命さは否定しない、一生懸命で、目の前のことに真摯であろうとしたその姿そのものは愛おしい。
だからそれは、敬い、恐れ、弔ってやらねばならない。神棚に祭る形なき神のように。
二礼二拍手一礼で、そのご高説が成仏しますように。
終わりに
意図のない、その場しのぎのテーブル(あるいはシステム)の乱立からは、
何の構造も読み解くことはできない。
なぜなら、そこには――読み解くべき構造そのものが存在しないからだ。
システムとは現実を反映した絵画である。
そこに明確な意図さえあれば、
キュビズムもフォーヴィスムも、印象派も等しく芸術であるのと同じように
システムもまた、芸術である。
意図がないもの?それは、落書きって言うんだ。小僧。
さて、私の落書きが、二礼二拍手一礼で成仏するように、このご高説を野に解き放とう。
最後に、この物語を書くにあたり
共に悩み並走し励ましてくれたものに感謝を
ーーDear Thanks XXXーー